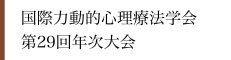プログラム紹介
大会テーマセッション
「成熟性の追究:力動的集団精神療法ライブセッション」
セラピスト:小谷英文(PAS 心理教育研究所理事長/国際基督教大学名誉教授)
コメンテーター:牛島定信(市ヶ谷ひもろぎクリニック 名誉院長)
ラルフ・モラ(個人開業/メリーランド大学 教授)
セス・アロンソン(ウィリアム・アランソン・ホワイト研究所 ファカルティ)
我々は青年期を越えることができるのだろうか。年齢に伴い心理学的能力は変化する。E.H.エリクソンの示す「親密性」「生産性」「自我の統合」の発達課題の力学的展開に迫りたい。力動的心理療法を受けているクライアントを大会参加者がロールプレイし、そのメンバーたちの集団精神療法をマスターセラピストがライブで行う。力動的集団精神療法は、個人の発達力動を可視化するのに優れた力動的心理療法である。世代の異なるクライアント、個々人の力学展開に成熟性に向けての鍵を探究する。
大会会長講演
「女性の成熟性」
講演:中村 有希(PAS心理教育研究所/東京医科大学・兵庫教育大学 非常勤講師)
司会:ジェイムス 朋子(京都橘大学准教授)
女性の社会進出が進む中、社会的役割を得ることで、心理学的な女性としての喜びは妨げられてはいないだろうか。女性の去勢コンプレックス、ペニス羨望が女性の成熟の妨げとなるというFreudの議論は、Jacobson, E、Honey, Kらによって、女性の成熟に向かう重要な精神発達の過程として見直されてきた。心理学的な成熟(psychological maturity)には男性にも女性にも終わりがない。ヒステリー研究に始まった心理療法の歴史は現代に至り、女性の成熟に向けた精神発達にどれほど迫れているのか。女性の独自性と相違性を考慮した女性の成熟に向けた精神発達の一つの姿を描くことが本講演の目的である。それは、女性特有の喜びとは何か、という問いに答えようとするものである。今や男性も女性も快感と喜びの体験を区別できず、世界的に快感原則から現実原則への展開は難しくなっている。反社会性人格スタイルが臨床の場だけでなく、グローバルな現象として目立つようになったこともこの展開の困難さを反映しているといえよう。快感原則を社会が後押しする中、力動的心理療法における女性の「愛する能力」と「働く能力」の発達展開、すなわち女性が人を愛し、愛されることの喜びを感受する過程を描く。
エドワード・ピニー記念講演
「成熟性の臨床精神分析理論:喜びの発達課題を軸として」
講演:小谷 英文(PAS 心理教育研究所理事長/国際基督教大学名誉教授)
司会:橋本 和典(国際医療福祉大学大学院臨床心理学専攻准教授/PAS心理教育研究所・IADP理事)
適応反応症、うつ反応が風邪のように流行り、発達障害、精神障害が多発する日常臨床には差し迫った治療ニーズがある。薬効が高まっているだけに、臨床成果に停滞があるとすれば、人格機能を上げる心理療法効果の問題を問わなければならない。薬効があるということは、人格反応の大きな揺れに対する守りがあるわけだから、人格機能修正の心理療法介入は明確な効果を上げなければならない。それが十分な展開に至らない。原因は、無効なアセスメントにある。見立てが診断に止まり、治療的展開を推し進める予後査定が弱い。どのような診断が付くにせよ治療的変化は可能だ。その可能性を現実化するための要因の取り出しがアセスメントであり、具現化するのが心理療法である。インテイク面接によるケースフォーミュレーションは、心理療法によって変化を進めることができる可能性を定式化するものであり、本格的な力動的心理療法はここから始まる。診断はその後の治療可能性を明らかにするプログノーシスを伴わなければならないが、精神科心理臨床ではこれが弱い。ケースフォーミュレーションは、診断を受けた後、そこに現実的などのような問題があるのか、それはどのような心理的な問題に由来しているのか、それ故に心理療法がどのような治療的変化を可能にするのか、そのために何をするのかを明示するものだ。心理療法契約に必要な事例性を明解にする治療者側のカードとなる。
アセスメントが無効なのは、変化の力動を捉えていないからである。誤った理解の事後性の査定や力動の分析に走り、病理や機能障害の状態にいかにして留まっているかの静力学査定に終わっている。如何に変化を起動し、どのように変化が進むかを分析する動力学査定が必要である。そのためには人システムの変化、すなわち成長と発達の筋道を示す基軸理論も、動力学的でなければならない。精神分析、心理療法を革新的に推進させたフロイトもロジャースも、当時最先端の生物学及び物理学を基に変化のメカニズムを捉えて、理論と技法を発展させた。現代の古典物理学から量子力学への躍進は、人システムの動力学的分析も躍進させている。人の変化の力動基軸は成長−発達の「成熟」にある。成熟とは、人が生物学的に必要十分に機能する変化過程である。幼児−子供−青年−大人のそれぞれに質の異なる位相の成熟があり、それが次の位相へ移る相転移変化を展開し死に至る。変化の動力学は、変化に作用する学習とその反作用の変化を押し留める静力学による抵抗も生む。この動力学と静力学の拮抗するなか、変化の運用エネルギーを高めていく分析協働作業を展開するのが力動的心理療法である。その変化の運用エネルギーが高まる際に現れる、人の反応が「喜び」である。
成熟展開過程の節目を表す喜びが、どのように起動し、刺激−反応による興奮の喜びから真の喜びへの展開を促すのか、快感原則の喜びが現実原則の喜びになる理論と技法の再構成を持って、人の成熟を図る力動的心理療法の基軸理論と技法を進展させたい。
懇親会
"Let's get together"
普段はそれぞれの場所で仕事をしている私たちが一堂に会する喜びを、ともに味わいましょう。会員の方、非会員の方、初めての方、オープン・プログラムのみ参加される方、どなたでも遠慮なくご参加ください。力動的心理療法に希望を見出す仲間が、ここにいます。
会場:ホテルリステル新宿(〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目3-20)
参加費:5,500円
全体ケースセミナー
コンダクター:小谷 英文(PAS心理教育研究所 理事長/IADP理事長)
事例提供:中村有希(PAS心理教育研究所/東京医科大学・兵庫教育大学 非常勤講師/大会会長)
IADP 年次大会のクライマックスが全体ケースセミナーです。一つの事例(ケース)を参加者全員で検討し、そのケースを前に進めることに挑戦します。参加者は、ベテランも初心者もファカルティも全員そのケースのスーパーヴァイザーとなって、ケースに参加し、アセスメントを行い、ケースフォーミュレーションを作り、ケースと向き合います。その中で、自身の臨床能力をブラッシュアップすることができ、事例から学ぶことができます。ひとりひとりが一つのケースに対して最大限自分の臨床能力を使い、それぞれの仮説が会場を飛び交い、互いに刺激しあうことで、事例の理解が深まります。
大会期間中に学んだ知識、理論、技術などをフルに使って、3日間の成果を確認しましょう。